社会保険労務士、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度のもとで生まれた資格です。社会保険労務士になるためには、社会保険労務士試験に合格するなど社会保険労務士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受ける必要があります。
受験資格:主に1.学歴、2.実務経験、3.厚生労働大臣が認めた国家試験合格の3つに分けられます。詳しくは、このリンク先をご覧ください。
受験料:9,000円
合格率:約3~9%
合格基準:選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と各科目ごとに定めます。各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となります(合格基準点は、合格発表日に公表されます。)
受験申込期間:厚生労働大臣の官報公示(毎年4月中旬)が行われてから5月31日までの間。
試験日程:年1回、8月の第4日曜日に実施
試験内容・科目:
| 試験科目 | 択一式 計7科目 |
選択式 計8科目 |
|---|---|---|
| 1.労働基準法及び労働安全衛生法 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 2.労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
10問(10点) | 1問(5点) |
| 3.雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
10問(10点) | 1問(5点) |
| 4.労務管理その他の労働に関する一般常識 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 5.社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | |
| 6.健康保険法 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 7.厚生年金保険法 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 8.国民年金法 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 合 計 | 70問(70点) | 8問(40点) |
試験会場:一部の都道府県で実施されています。
合格発表日:例年11月上旬になります。
実施機関・問い合わせ先:
厚生労働省/全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階
TEL 03-6225-4880
FAX 03-6225-4883
1.社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
- 申請書等の提出代行
- 申請等についての事務代理
- 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
- 都道府県労働局における男女雇用機会均等法、パート労働法及び育児・介護休業法の調停の手続の代理
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理
(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要) - 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導
2.社会保険労務士の顧問料(相談費用)
継続的な顧問料としての相談費用は、月額で1万円~5万円が相場のようです。
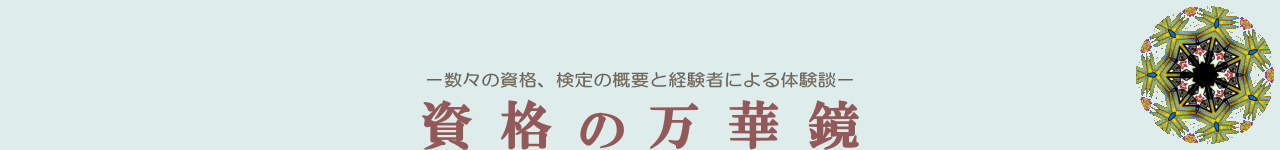





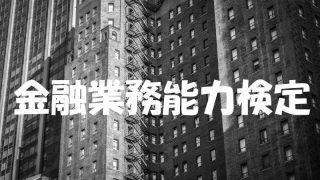


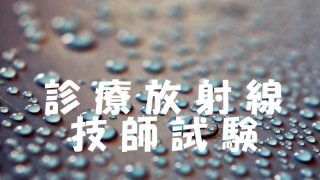



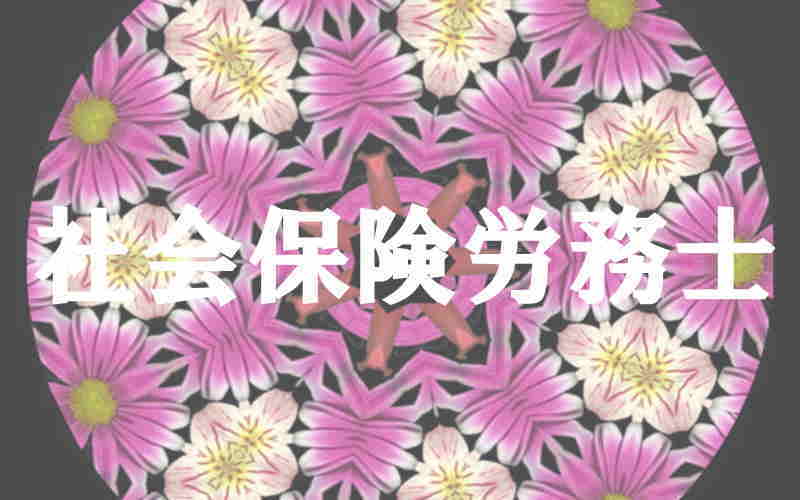

コメント
私はIT企業で人事を担当しており、「社会保険労務士の知識があれば業務の幅が広がる」と思い立って受験を決意しました。ただ、私の勉強法は少しユニークで、最初から机に向かうのではなく、日常生活のあらゆる場面に学習を組み込みました。
まず通勤中は耳学習。公式テキストを自分の声で録音し、電車や歩きながら何度も聞き流しました。昼休みには同僚に「今日の社会保険クイズ」を出して、アウトプットしながら記憶を定着。自宅では冷蔵庫や鏡に条文や数字を書いた付箋を貼り、無意識に目に入るようにしました。
勉強時間は平日2時間、休日は6時間ほど。特に苦手だった労働基準法の細かい日数や金額は、語呂合わせソングを作って自分で歌いながら覚えました(家族には少し不評でしたが…)。試験3か月前からは過去10年分の過去問を繰り返し、間違えた問題は理由まで言えるようにノート化。
本番当日は「聞き覚えた自分の声」が頭の中で流れる感覚があり、不思議と落ち着いて解けました。結果はギリギリではなく余裕を持って合格。振り返ると、机にかじりつくだけでなく、生活全体を勉強モードに変えたことが勝因だったと思います。今では業務に直結する知識が増え、周囲からも「相談しやすい人」と言われるようになりました。