ビルを経営するには、賃貸ビルの企画・立案からテナント募集、運営、管理まで、不動産についての幅広し知識が必要で、これらの知識と経験を備えたビル経営管理士は、総合不動産投資顧問業登録の際の人的要件にもなっている。
[expander_maker id=”1″ ]
実務経験の有無に関係なく、誰でも受験できます。 ※ただし、試験合格後の登録には実務経験んどが必要になる
受験料:33,000円(税込)
合格率:直近では約67〜76%と比較的高水準で推移(2024年 70.9%)
試験日程:12月中旬
試験内容・科目:
①賃貸ビルの企画・立案に関する知識
・事業企画(市場調査、敷地選定)、ビルの商品企画(テナント構成、建築意図)、ビル建設と法規制、コンストラクションマネジメント、不動産投資理論、不動産事業の税務と会計及び事業分析、不動産の証券化に関する仕組みと法制及び税制、長期事業収支計画・長期維持管理計画(ポートフォリオ)、不動産特定共同事業、業務管理者実務、 不動産投資顧問業登録制度、デューデリジェンス(エンジニアリングレポート)、デューデリジェンスの調査項目と結果分析、不動産投資市場及び不動産流通市場の知識及び分析、金融市場の動向に関する知識及び分析、遵法性の確保、アカウンタビリティー、プレゼンテーション、リスクマネジメント等を行う上で必要な専門知識について
①賃貸ビルの賃貸営業に関する知識
賃貸条件の設定、テナントの募集、テナントとの契約手続、テナントの入退去時の対応、テナント契約管理(退室・増室・同居・転貸・滞納等)、賃料・共益費の改定、テナントニーズの把握、その他(催事企画など)、リーシングマネジメント等を行う上で必要な専門知識について
③賃貸ビルの管理・運営に関する知識
プロパティマネジメント体制・管理企画業務、資産管理業務、ビル運営管理コスト、エネルギーコスト管理、館内規則の策定、管理委託契約締結、委託管理業者管理、業務品質評価、業務品質管理、ビルメンテナンス(日常管理業務:施設・設備・警備・防災・環境衛生等)の管理、建物維持保全業務(点検、修繕、モダナイゼーション等)の管理、各種許可・届出などの手続き、立入検査対応管理等、日常管理業務に関するテナントなどへの対応管理、コンストラクションマネジメント、ライフサイクルコストマネジメント、複合用途のプロパティマネジメント等を行う上で必要な専門知識について試験会場:
札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡 の13か所
合格発表日:1月末
応募期間:9月~10月
実施機関・問い合わせ先:
一般財団法人 日本ビルヂング経営センター
〒100-0006東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル2F 204区
TEL03-3211-6771
https://www.bmi.or.jp/index.html
[/expander_maker]
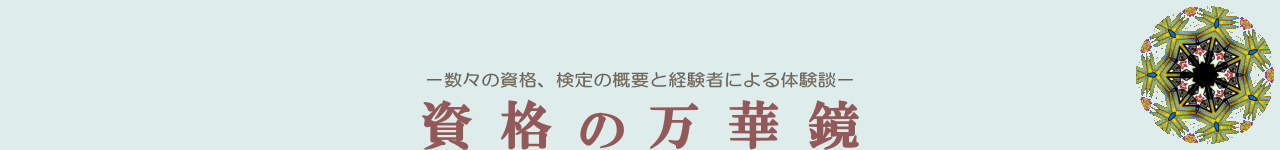
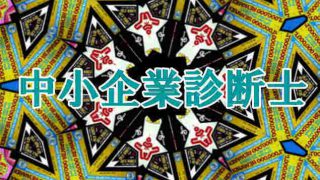





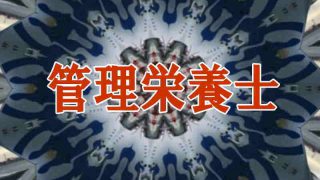
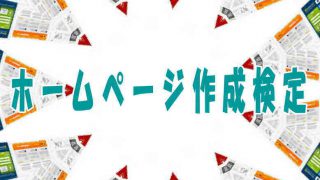



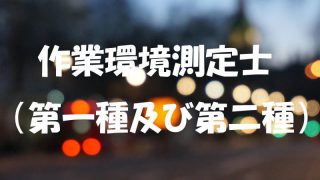


コメント
私はビル管理会社に勤務しており、キャリアアップのためにビル経営管理士試験に挑戦しました。最初の受験は正直、失敗に終わりました。仕事が忙しいことを言い訳に、テキストを一通り流し読みするだけで臨んでしまい、過去問演習も数年分しか手をつけませんでした。結果、法令や会計の細かい数字問題で手も足も出ず、不合格。悔しさと同時に、勉強法を根本的に見直す必要性を痛感しました。
翌年の再挑戦では、まず学習計画を徹底。平日は朝30分の早起き勉強と通勤中の暗記カード、休日は5〜6時間を確保しました。過去10年分の過去問を解き、間違えた箇所は「なぜそうなるのか」を条文や参考資料に立ち返って理解。特に不動産関連法規やテナント対応の実務部分は、実際の業務経験とリンクさせて整理しました。また、模擬試験を受けることで時間配分の感覚を掴み、本番に近い緊張感を体験できたのも大きかったです。
試験当日は、前年の失敗が逆に自信につながりました。「今回はやれるだけやった」という思いで臨めたからです。結果は合格ラインを上回り、念願の合格通知を手にしました。失敗を経験したからこそ、自分に合った勉強法を確立できたと思います。今では試験勉強で得た知識を業務に活かし、テナント対応や経営計画の場面で「勉強していてよかった」と実感しています。